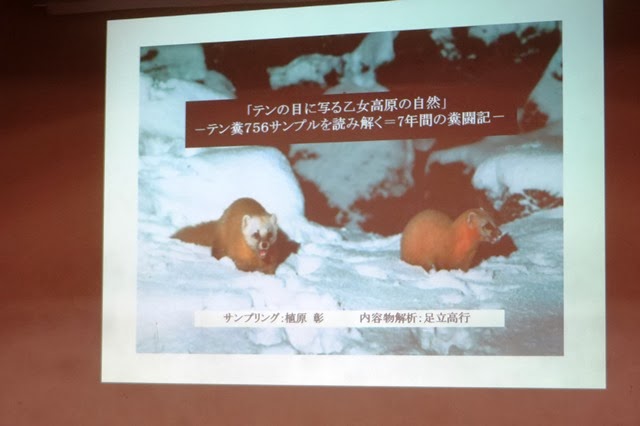11日正午過ぎ、吉野屋の一幸さんの車で上ノ原まで送ってもらう。眼前に、抜けるような青空と白銀の世界が広がる。そこに、雪山遊びの若人たちの姿。見事なカラー・コントラストだ。(写真左)

早速、持参のかんじきにはき替えて出発。先行のスノーシュー組によって径が踏みならされていて歩きやすい。カラマツ林の梢の辺りから野鳥の囀り。寒気をついて耳に届く響きが心地よい。緩やかな上りをしばらく行くと、幽かにせせらぎの音が聞こえてくる。大幽沢と手小屋沢川の合流地点だ。(写真左)
鳥の囀りとせせらぎの響きに、かんじきで雪を踏む音が混じる。大自然を舞台にした静かな合唱!少しずつ傾斜がきつくなって、最後の百㍍弱がちょっと手ごわい急坂。もう少しの頑張りと一気に登りつめる。眼前に現れたのは、まるで狩猟民族の住居跡かと思わせるような石窟。(写真左)
入口まで近づいて中をのぞき見ると、期待にたがわぬ見事な氷筍(ひょうじゅん)が林立。差し込む冬の日差しにキラキラと輝いている。(写真左)
後から上がってきた一行から「これまで見た中で一番きれい」と歓声があがる。聞けば、「いつも、大寒から今頃にかけて毎年見に来ている」由。腰かけて一服。用意周到の古高さんから「熱いの一杯どうぞ」とコーヒーカップ。これが何とホットウイスキー。一生の思い出になるほど旨かった!
帰路は下りなので余裕で、樹間から遠望する谷川岳や朝日岳の雄姿を堪能。(写真下)先行組が作ってくれた尻ぞりコースの直滑降を楽しんだりしながら童心に帰るのであった。
以下は、視察行を踏まえた参考情報・アドバイス。
① 道標看板によれば片道1,850㍍。往路は休憩なしで1時間15分、復路は同45分。
② 最後の急坂対策も兼ねて、かんじき+ストック併用をお勧め。
③ 小学校低学年以下の児童には厳しいのでは。上ノ原で雪合戦、ソリ遊び、などお勧め。
④ 大人も子供も必携は、靴底用ホカロンとサングラス。温度計、冬芽観察用のルーペ、カメラなども携行すると楽しさ倍増。
以上(2014.2.13、清水記)